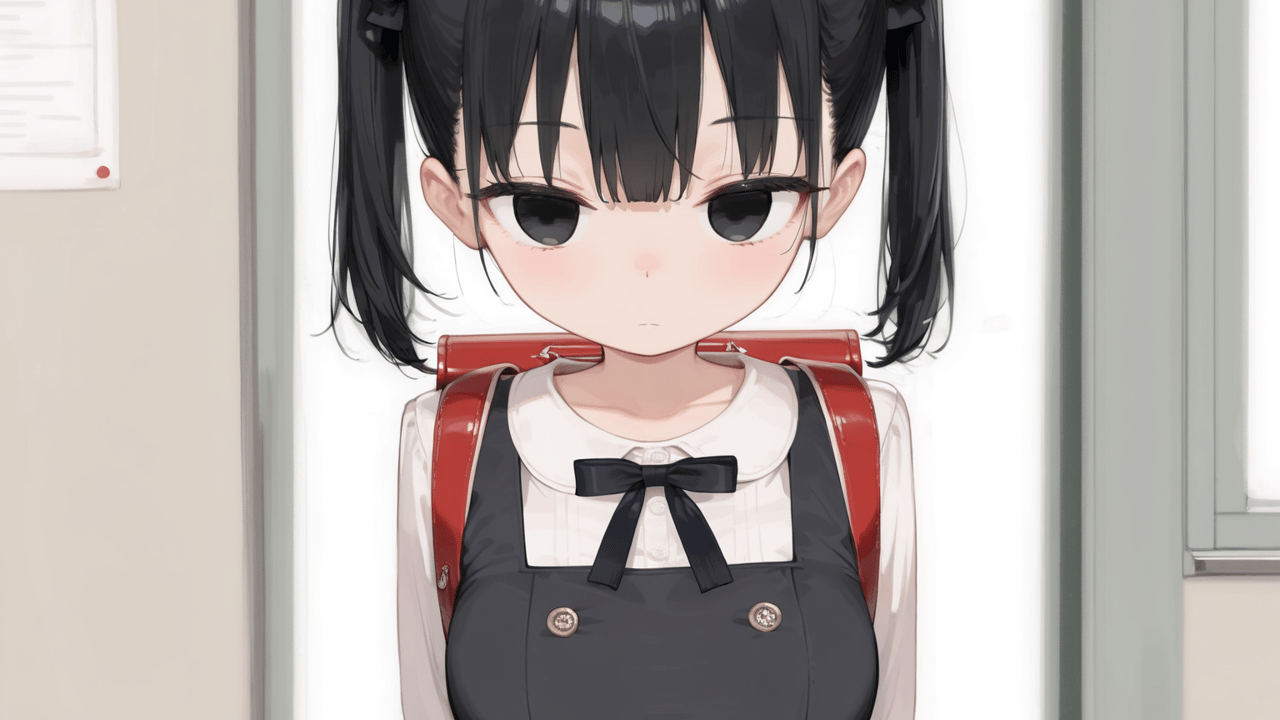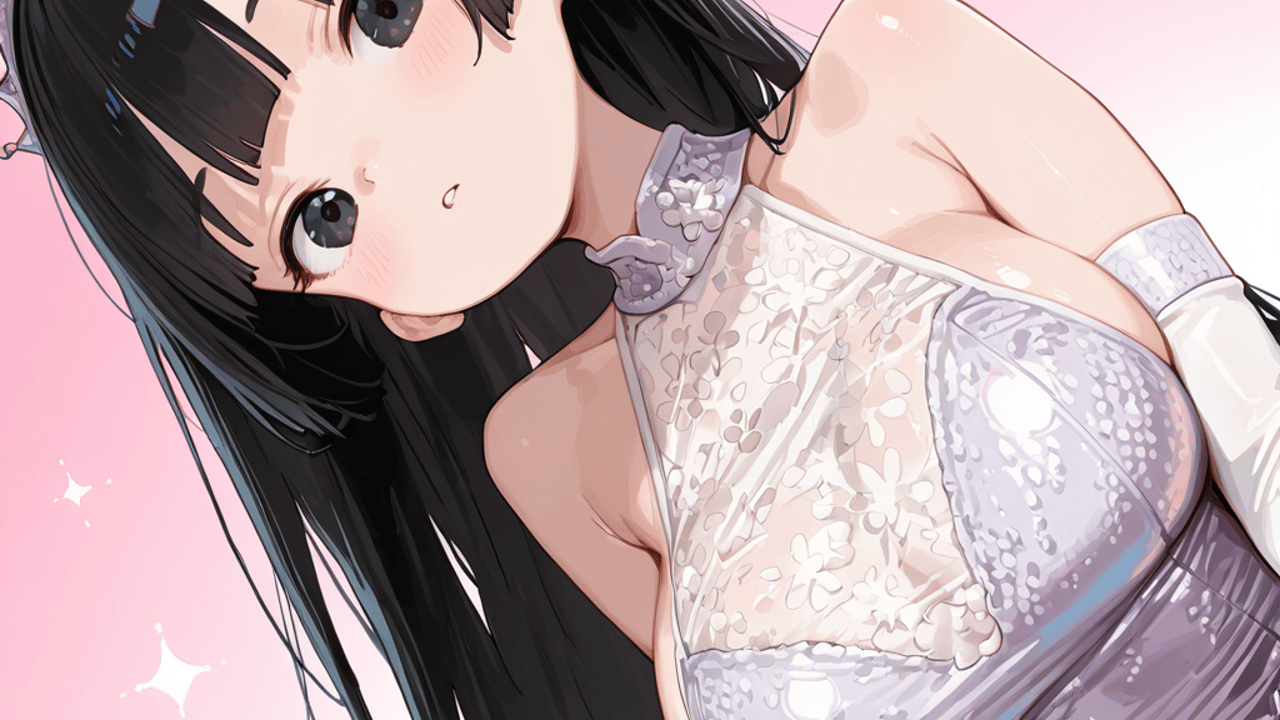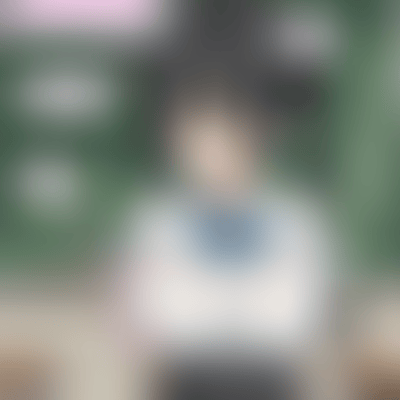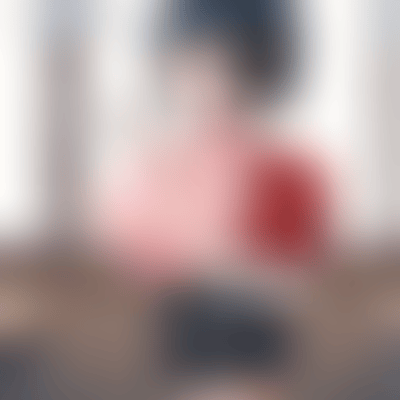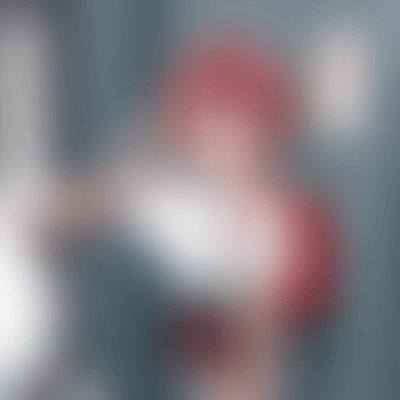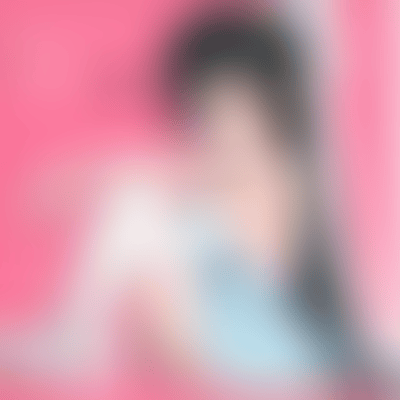藤田 樹 15歳Iカップ あっさり寝取られる
通学路の角で、樹の姿が見えた。彼女は白いシャツに赤いリボンを結び、膝丈の紺スカートが朝の微風に揺れていた。白いクルー丈靴下が足首を覆い、制服はきちんとしているのに、リボンの結び目がわずかに乱れ、彼女の押しに弱い心を映しているようだった。長い黒髪は朝の光に鈍く光り、彼女は小さなバッグを握りしめ、うつむき加減で立っていた。視線は地面に落ち、唇を軽く噛む仕草に、昨夜の戸惑いがまだ残っているようだった。 その横に、リョウがいた。坊主頭が曇天の下で鈍く輝き、黒い詰襟制服は上ボタンが外れ、袖がだらしなくまくられていた。彼は大げさに肩を揺らし、わざとらしい笑みを浮かべて樹に話しかけた。「よっ、樹! めっちゃ可愛いな! 今日も俺と一緒に学校行こうぜ、超バッチリだろ!」その声は中学生らしい幼稚な自信に満ち、ダサい自慢が朝の静けさを破った。 樹の肩が小さく縮こまり、バッグを握る手が強張った。「え、一緒に…?」彼女の声はか細く、ためらいが滲んだ。「う、うん…でも、ちょっと…急に言われても…」彼女の目はちらりと横に逸れ、通り過ぎる生徒たちを追ったが、主人公の存在には気づいていない。リョウの押しに流されそうになる自分を、どこかで止めたいと願うような、かすかな抵抗だった。 主人公は数メートル離れた木の陰に立ち尽くし、胸が締め付けられるように痛んだ。乱れた前髪が目に落ち、汗で額に張り付いていた。ネクタイを握る手は震え、昨夜の絶望が再び蘇った。「樹…なんでアイツと…」彼は独り言のように呟き、声が途切れた。校門での告白、雨に濡れた樹の姿、リョウの割り込み——全てが無力感となって彼を押し潰した。 リョウがさらに声を張り上げた。「な、樹! 俺と一緒なら毎日楽しいぜ! 俺がドーンと保証するから!」彼は大げさに胸を叩き、ニヤニヤと笑った。樹はスカートの裾をそっと握り、肩をさらにすくめた。「え、毎日…?」彼女の声は震え、曇り空の下で小さく響いた。「うーん…まあ、いいけど…たぶん…」その言葉は、主人公の心に冷たく突き刺さった。 「樹…もう届かないのか…」主人公は木の幹に手をつき、膝が震えた。「アイツのせいで…俺の気持ち…」声は途切れ、曇天が彼の視界をぼやけさせた。樹のシルエットがリョウと並んで遠ざかり、赤いリボンが朝の風に揺れる。彼女の声が遠くから聞こえた。「リョウ、ちょっと…そんな急に…だろ…」だが、リョウは笑い声を上げ、彼女の肩に手を近づけた。「樹、今日も俺がエスコートしてやるぜ! 超カッコいいだろ!」 主人公は動けなかった。樹の赤いリボンが視界の端で揺れ、彼女のシルエットはリョウと一緒に通学路を進んだ。曇り空の下、主人公の心は届かない朝に閉ざされ、静かな絶望だけがその場に残った。